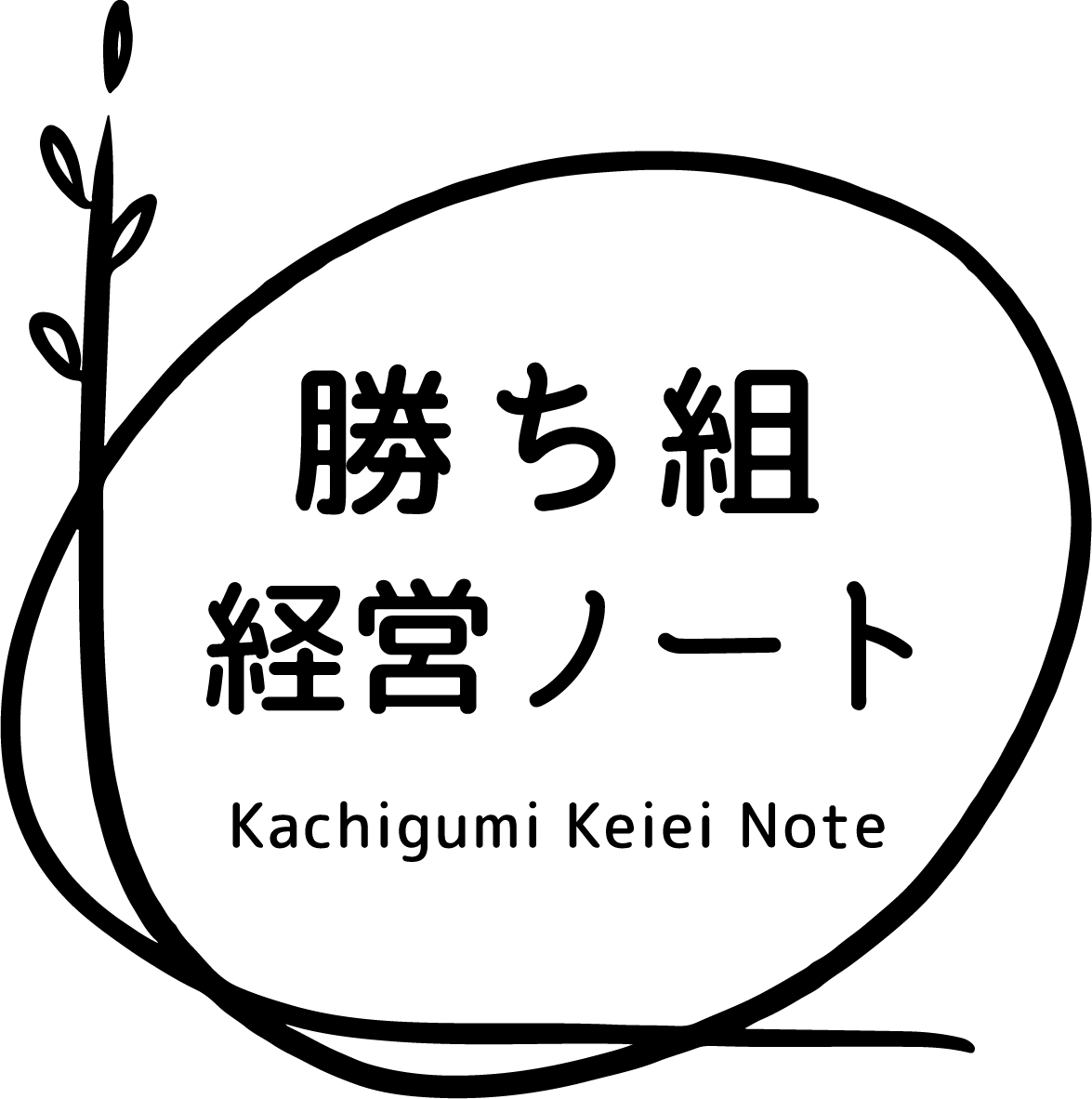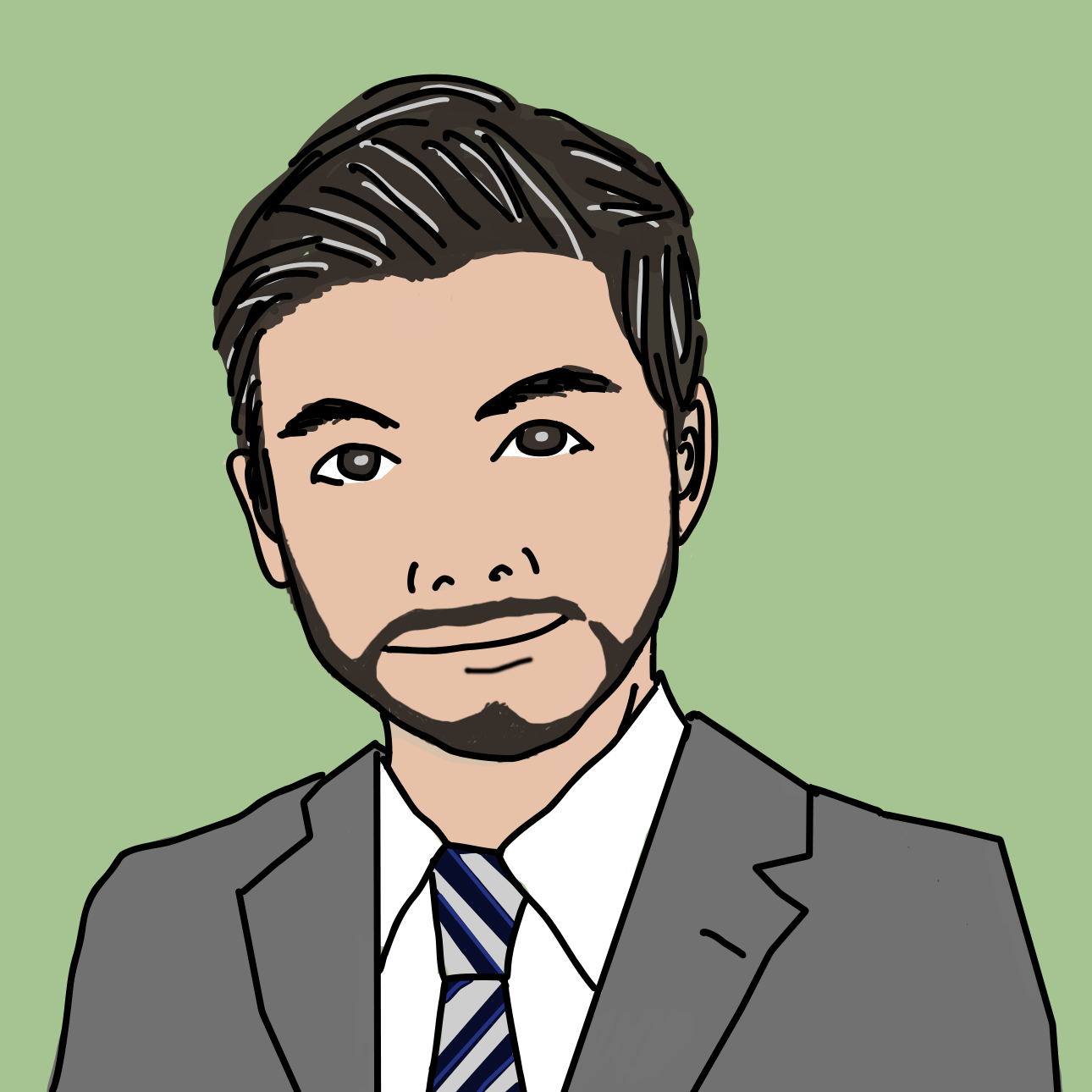下記の条件が発生した時には
 つのだ
つのだすることが賢明と言えます。
- 致命的な失策
➨事業がスタートして一年以内に致命的な失策が分かった場合、尚且つ、そのことが最大の要因となり収益が見込めないときには即座に撤退の準備に入ること。 - 収益が見込めない
➨事業開始後、黒字化が3年以内、初期投資の回収が5年以内にできないと判断したら迷わず撤退を決定すること。 - 市場規模が長期縮小化
➨事業開始後に予想していた市場規模が、将来にわたり長期に縮小することが根拠と共に明らかとなった場合、撤退の方向性で検討すること。 - 競合相手に勝てない
➨事業開始後、予測していなかった競合相手が出現したり、もともとの競業相手に圧倒的な競争力が増した場合、全面的な戦略の見直しを図ること。しかし、図った結果、自社の戦略の優位性が見出せないときは撤退を決意すること。 - 自社の経営力が急低下
➨自社の経営資源(リソース)に極端な枯渇状況が生まれた場合、まずはその手立てを考えるが、どうしても難しいと判断した場合は撤退も辞さない。
1.致命的な失策
事業がスタートして
一年以内に致命的な失策
が分かった場合。
尚且つ、そのことが最大の要因となり



ときには即座に撤退の準備に入ることが大切です。
起業家精神が旺盛な上、
強い確信をもって新規事業を
しながら立ち上げる。



このことには素晴らしい面もありますが、


素晴らしい点は、
信念と情熱のすごさが事業を立ち上げる際の原動力
となったり、周囲の関係者、協力者を巻き込む
とてつもない求心力



となる点です。
一方、危なっかしい面は、
で、これから手掛けようとするビジネスの水面下に潜んでいる
リスクや背後にある問題点などをほとんど精査しない



コトを強烈に推進していってしまう点です。
要は、事前の調査・分析を“意図的にしたがらない”
といった部分を指します。
具体的には
- 「ケーススタディ」
- 「フィージビリティスタディ」
がほとんどうわべっつらだけ。
- ケーススタディ(Case study)
-
現実に起こった具体的事例を分析、検討すること。
- フィージビリティスタディ(Feasibility Study)
-
新規事業や新商品を開発、展開していく上で、主に自社の経営資源で実際に実現可能かを検討すること



この二つがなおざりになっていることが多い。
※ちなみに、「なおざり」はいい加減なうえに何も対応しない、「おざなり」はいい加減ではあるものの何らかの対応はするので大きな違いがあります。
結果、
を招きます。
このような失策は、私自身も経験しましたし、
自己実現欲求の強い



周囲の起業家にもたくさんおりました。
2.収益が見込めない
事業開始後、
- 黒字化が3年以内
- 初期投資の回収が5年以内
にできないと判断したら



迷わず撤退を決定すること。
「黒字化3年以内」と「初期投資回収5年以内」は
にするとよいでしょう。
- 業種によっての初期投資規模
- ビジネス展開における戦略性
によっては黒字化年数が



という部分はあります。


しかし、3年、5年という指標は
撤退を決断する上での重要指標
と言ってよいでしょう。
私も数えきれないほどの新規事業を手掛けてきました。
気合い論だけで突き進んだ



結果、大きなダメージを受けたこともありました。
事業を始めるときの決断よりも
が求められます。
特に面子を保つため、
事業を続行させてしうと



益々、厳しい撤退環境となってしまいます。
(撤退したくともできないでいる状態)ですので、
予め事業をスタートする際に、
ことが賢明でしょう。



なぜなら、合理的に撤退の意思決定ができるからです。
勇気も覚悟もさほど必要とならないからです。
そして、周囲の関係者も納得しやすいからです。
3.市場規模が長期縮小化
事業開始後に予想していた市場規模が、
将来にわたり長期に縮小する
ことが根拠と共に明らかとなった場合



撤退の方向性で検討すること。
市場というものは“生き物”です。
そして、事業というものは市場と共に生きています。



同時に、市場の主役はお客様です。
新規事業というものは、
これまで顕在化していた市場にあった顧客ニーズを捉えて始める
- これから生まれる市場、
- もしくはこれから創造していく市場



の潜在的な顧客ニーズに仕掛けていくビジネスです。
ところがこの潜在ニーズが消滅してしまった、
もしくは大きく縮小してしまっている
と予測できるときには
しかも、その縮小の予測は長期にわたり続くとなれば
新規事業は“日の目を見ない”



ということになります。
特に注意が必要なのは、
昔から言われている



です。
このキーワードは「破壊」を意味しています。
低コストなIT技術を利用した新たなビジネスで、
ことを意味しています。
これから先、DX化が加速し



可能性があるでしょう。
簡単に言えば、
旧態依然として存在していた需要は大きく変化
する可能性があるわけで、
もし、市場と顧客ニーズを見誤った時には



して一気に致命傷となるでしょう。
*デジタルトランスフォーメーション(DX/Digital Transformation)とは、IT技術の広まりにより働き方や市場、生活など社会そのものを変えること。
デジタルディスラプションの事例では
- 「ブロックバスター」
- 「Netflix」



がよく紹介されます。
IT技術が普及しイノベーション(変革)が起き、
Netflixがサブスクリプションサービスを開始しました。





それによって
- 「レンタルショップに行く必要がない」
- 「定額で好きな動画が無制限に見られる」
というDXが生まれたのです。
その結果、
アメリカ大手のレンタルショップ
Netflixが躍進しました。



まさに、ITによってデジタルディスラプションが起きたわけです。
これからは、
によって同じようなデジタルディスラプションが起こる



ことは容易に想像できます。
新規事業を仕掛けるときにはAIによって
を的確に予測する必要があるでしょう。
4.競合相手に勝てない
事業開始後
- 予測していなかった競合相手が出現したり
- もともとの競業相手に圧倒的な競争力が増した場合



全面的な戦略の見直しを図ること。
しかし、図った結果、
ときは撤退を決意すること。
誰しも新規事業を考えると
真っ先に競合相手を頭に浮かべます。



そして、必死に状況分析をします。
そして、勝算ありとなって準備に入るわけですが、
意外や意外、
当然と言えば当然です。



市場も顧客もアップテンポに変化しているからです。
一番、厄介なことは
時でしょう。



私の経験においても何度かありました。
「まさか?あの会社が参入してきたの?」と驚き、
時に慌てたりしたものです。
特に異業種からの参入の場合は
徹底した差別化戦略
をとっていることが多く、



脅威にすら感じることも多々ありました。
新規事業を開発しようとすると、大方
「ファイブフォース分析」(five-force-analysis)
などをすることが定石となっています。
*ファイブフォース分析(Five-force-analysis)とは、業界に存在する5つの脅威をもとに、事業や企業戦略を分析するフレームワークです。「購入者の交渉力」「販売者の交渉力」「競合他社の競争力」「新規参入の脅威」「代替商品の脅威」の5つです。



しかしそれでは、不十分といいましょうか、安心はできません。
なぜなら、おいしいマーケットには
が複数あるからで、



それらの企業動向は中々、調べても分かりません。
もし、新規事業をスタートして
途中から脅威となる競合相手が現れたら
その後の展開において



を検討する必要があります。
やみくもに対抗して戦おうとすると
こともあるのです。


*レッドオーシャン(Red Ocean)とはすでに競合が市場内に多数存在し、競争が激しくなっている市場を表す。新規参入企業が多く、価格競争や機能面での競争が激化している状態。値引き合戦は象徴的な現象であり、『血で血を洗うよう』な激しい価格競争が行われている。
脅威となる競合相手が現れたら
即座に、全面的な事業戦略の見直し
をすることです。
そして、見直しても事業の継続発展が難しいとなれば



ことは正しいと考えています。
5.自社の経営力が急低下
自社の経営資源(リソース)に
極端な枯渇状況が生まれた場合、
まずはその手立てを考える



が、どうしても難しいと判断した場合は撤退も辞さない。
- 起業家が一人で立ち上げる新規事業
- 社内プロジェクトから立ち上げる新規事業
- 企業間で提携して立ち上げる新規事業
いろいろなケースがあります。
どのようなケースであっても
「何をやるか」と同じくらい「誰がやるか」



は事業の成否を決める重要な要素です。
よくあるケースで言えば、
が何らかの理由で離脱することになってしまい



途端に事業が失速する、といったことです。
その他にも予定していた新規事業の資金が
何らかの理由から突然、枯渇する
といったこともあります。
また、せっかく始まった事業が



ストップせざるを得ない、といったこともあります。
つまりは、事業開始当初
となった場合には、大きな損害賠償や
最悪の実態である倒産
といった悲劇にならないためにも、



勇気ある撤退をしっかりと考えることが必要です。