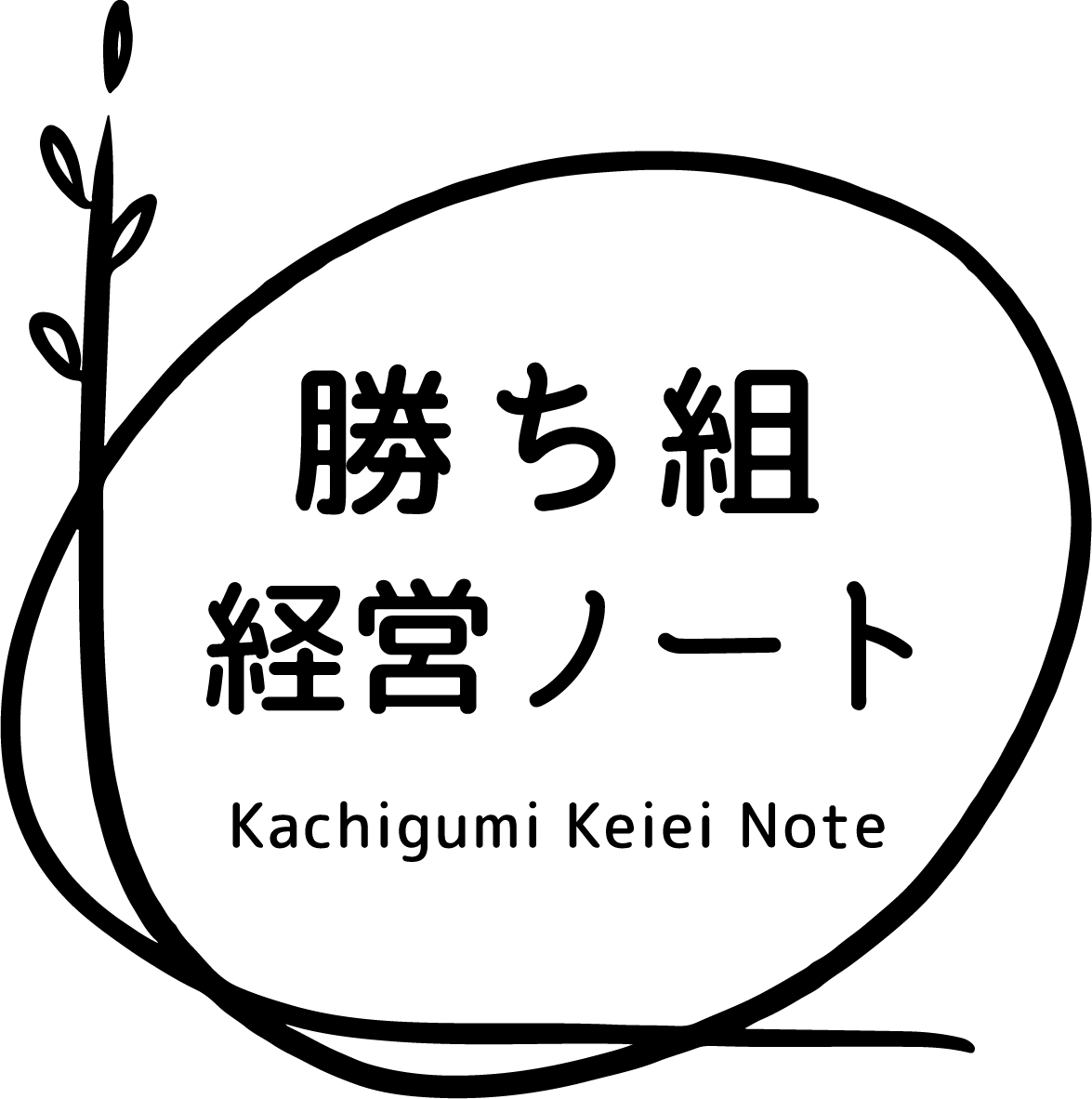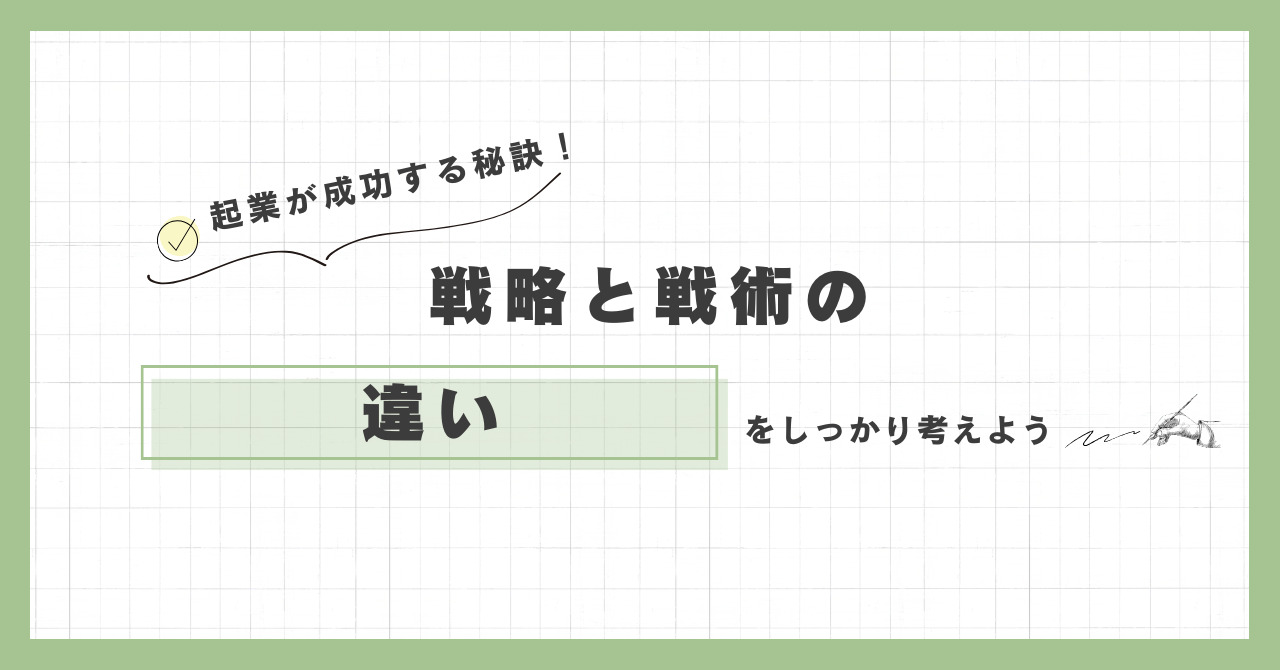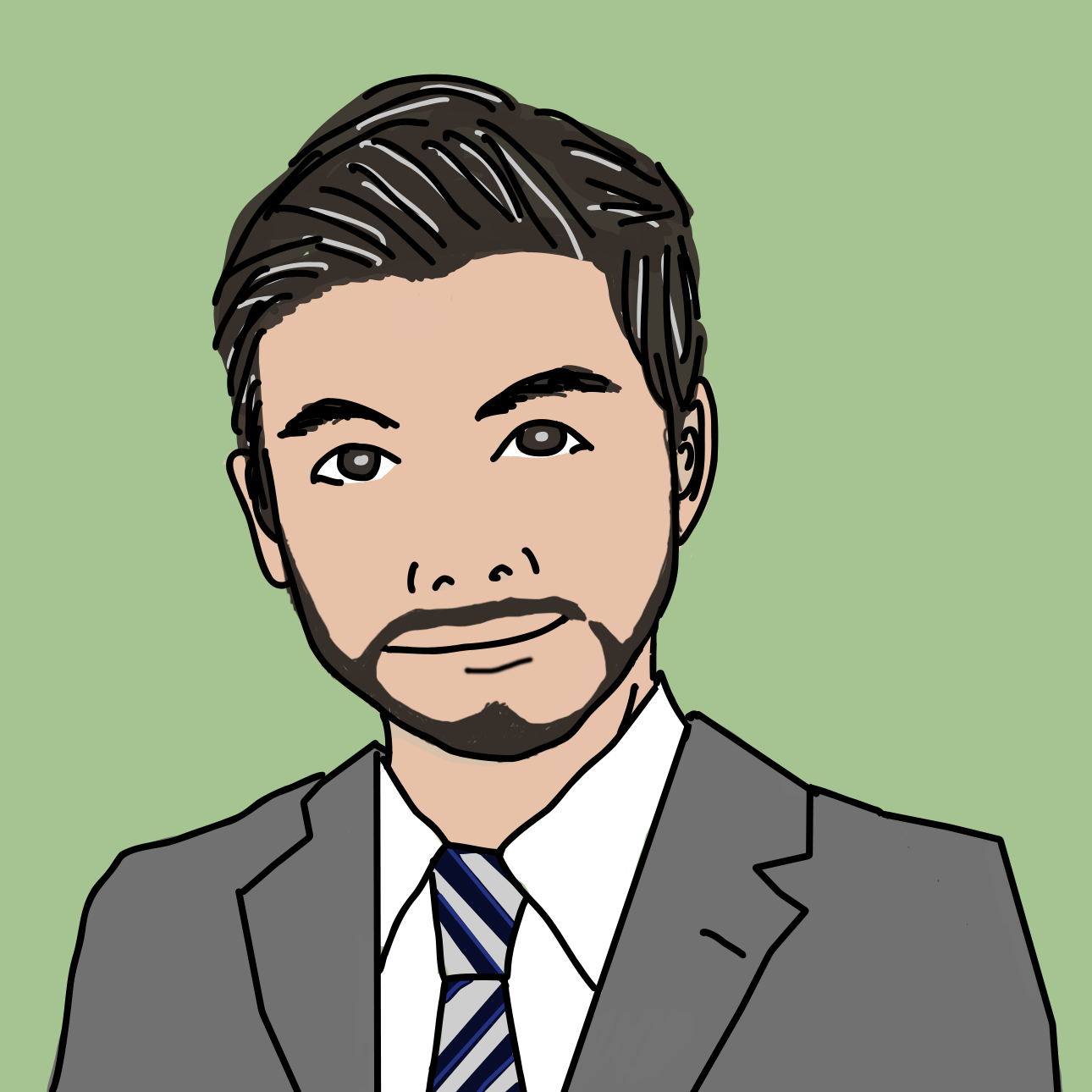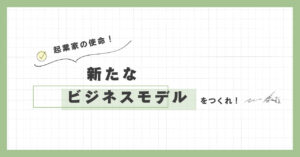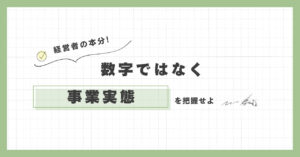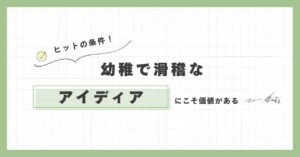今回、解説しますのは起業時の意思決定における力点についてです。
 つのだ
つのだ私自身、起業自体はおそらく50近く手がけてきました。
その際に、常に念頭に入れていたのは
- 「方向性」
- 「方法論」
のことでした。


《本編の結論》
‟起業の成功は方向性こそ肝心要!”
❖起業にとって最も重要なことは‟方向性”が正しいこと。
つまり、「時代に乗っているか?」、「市場に受け入れられているか?」そして、
である。
❖‟方法論”が先行してしまうと起業は途中で頓挫する!方向性と方法論をはき違えてはならない。
1、致命傷となる方向性の過ちとは?
起業をしようとするとき確かな方向性を定めていないで見切り発車をするケースが結構多いように思います。



例えば、これからある事業を立ち上げようとするA氏がいたとします。
そのAには起業する事業に対して以下のような意気込みを持っていました。
- 「自分はこのような実績を持っている」
- 「自分はこのようなノウハウを持っている」
- 「自分は自己資金と外部から調達できる資金の目途がついている」
- 「自分にはいろいろな分野のブレインがいる」
- 「予め起業育成セミナーも出たし、事業計画書も指導してもらった」
- 「だから成功できる自信がある」
このようなことをA氏が語ったとしましょう。


この自信はとても頼もしい限りではありますが、肝心な事業自体の方向性はどうなのでしょうか?



私はこの起業家A氏に以下の3つの質問をするでしょう。
- その事業はSDGs、AI、少子高齢化など「時代の流れ」に乗っていけるか?
- その事業は物価高のインフレ基調で、モノ余りの飽和状態となっている「市場の動向」に受け入れてもらえるか?
- モノからコトへの価値観、所有からシェアの志向に変わっている「消費者のニーズ」に適っているものなのか?
このように、「時代の流れ」、「市場の動向」、そして、「消費者のニーズ」の3点



つまり方向性について確認をするでしょう。
始めようとしている事業がこの3つの観点から
“やっていけると判断できる”
のであれば方向性は概ね正しいと言えます。
もし、3つとも‟マッチしていない”となれば、方向性はぶれているか逆行していると言えます。
その結果、事業は失速や蛇行、もしくは頓挫か破綻といった事態に陥る可能性が高いと考えます。
2、方向性は戦略の意思決定、方法論は戦術の行動調整と言える
先に紹介したA氏の自信の中身は事業展開上の方法論の範疇に入ります。



中身一つ一つは、とても有効なものです。
ところが、いくら有効であっても事業の向かう先が‟的を外しいる”となっていれば
方法論の持つ価値は生かされることがないのです。
間違っているわけでもありません。
ただ、言いたいことは、方法論に強みがあったとしても、起業の最終的な成功要因にはならないということ。
あくまでも成功要因は‟方向性の正しさ”にあるのです。
尚、私はこの方法論における「アレンジメント軸」と呼び、方向性を「ベクトル軸」と呼んでいます。


例えで言えば、親衛隊が敵を倒そうとして、うっそうと茂る森に向かって歩き出すとします。



その時、襲われないための武器は十分にある。
部隊員は実力者がそろっている。
しかし、指揮官の稚拙な考え、思い付きで間違った方向に動く判断をしたとすると、
向かった先は苦難の道、最悪生死を決定づけてしまう道となるかもしれません。



大変なリスクを背負うことになるのです。
案の定、隊員たちは疲労困憊に陥り、中にはけが人や病人までも多数出す結果となってしまい、
ついには目指したゴールにたどり着くことができませんでした。


たとえ方法論は長けていたとしても結局のところ役に立たなかったことになります。



起業も同じことが言えるのです。
ベクトル軸にある方向性というものは、ひとたび動き出すと引き返すことができないか、
もしくは、引き返すとなれば相当な犠牲を払うことになる。
いわゆる生命線。
そして、その方向性が大きく間違っていたとなれば命取りとなる。
最悪、倒産といった結末にも至るということです。



これが方向性の特性です。
一方、アレンジメント軸にある方法論というものは、主にやり方を意味します。
- 方法論と言うものは動き出してから必要に応じて都度、変更すればよい。
- また、方法論には武器としての位置づけもあります。
- 武器は状況に応じて使えばよい。必要に応じて使えばよい。



それがアレンジメントの性質なのです。
始動してから変更すること、使い分けること。
別の言葉であえてわかりやすく言えば、これから起業しようとする際の方向性は‟戦略”と呼んでよいでしょう。
そして、方法論は‟戦術”と言えるでしょう。
戦略は……「目標を達成するための計画のこと」
戦術は……「戦略を達成するためにやること」
戦略は事を始める前にしっかりと思考(ゴール設定と方針)することが重要です。



思考の結果、下した決断は撤回できないと心得ること。
一方、戦術はある程度、概略(方法論の骨子=どうやるかの大筋)を考えたら
行動を優先することが秘訣です。


もともと方法論と言うものは行動しながらブラシュアップするものであり、
調整を繰り返していけばいくほどブラシュアップされるのです。



結果、成功の確率を高めていくことに繋がります。