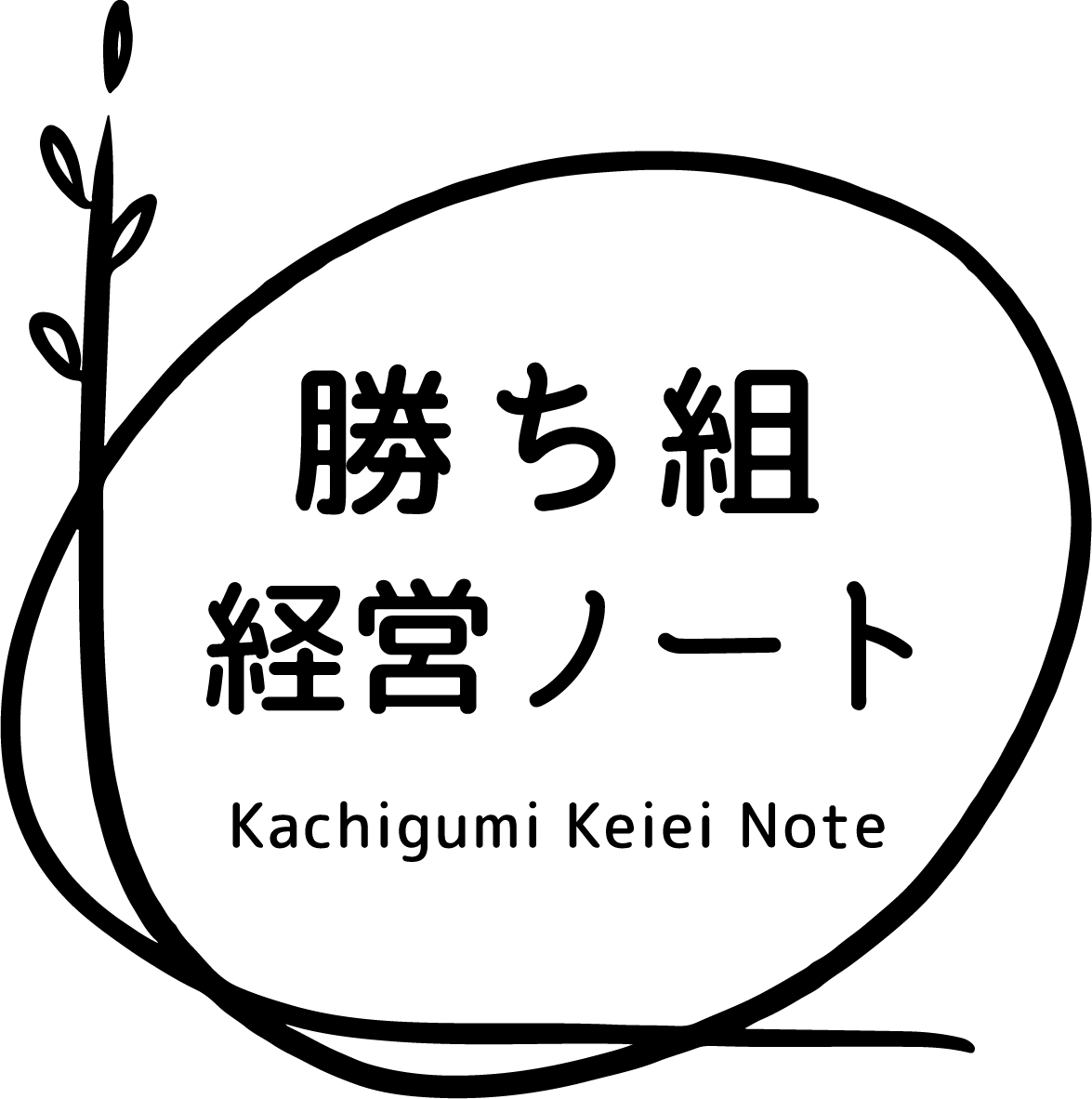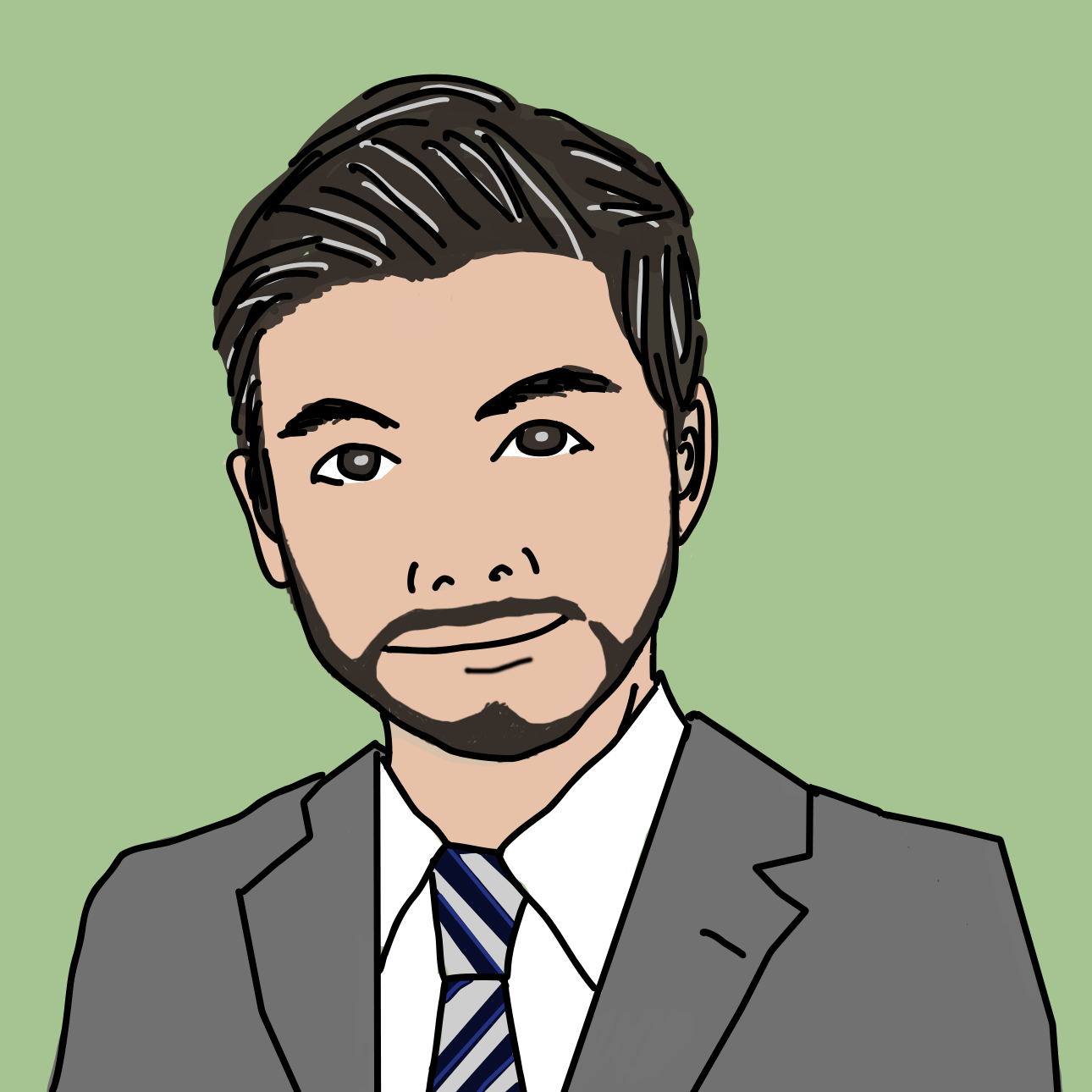つのだ
つのだ「経営の勘どころ」の第四回は、‟起業編”です。
経営の勘どころ初回はこちら
» 「給与はお任せします」と言う人間を採用してはいけない
まず最初に「起業に対する私の基本的な見解」を申し上げておきます。
起業時の心得として最初に頭に浮かぶ言葉は
「動機善なりや、私心なかりしか」
です。
ご存知のことと思いますが、京セラの創業者であり、一時経営破綻した日本航空の再建を手がけました稲盛和夫氏の言葉です。
何か事を始める時には自身に
と問いてみる、と解釈しています。



つまり「動機が純然たる善であれば着手せよ」ということでしょう。
勿論のこと、考え方としては正しいと思っています。
ところが実際の起業時の動機というものはそれほど純度の高いものではないように思います。


起業時の動機
- 「大金持ちになりたい」
- 「社長としてビックになりたい」
- 「世間を見返してやりたい」
- 「人からすごいと言われたい」
- 「自分のクルーザーを持ちたい」
- 「豪邸に住みたい」
- 「優良企業をつくり早期にM&Aで売り別のことをやりたい」
など、いろいろあるでしょう。



私の考えは
「起業時には“野心”があって良し、しかし、起業家からいずれ経営者になっていかなければならない。経営者になるには‟良心”が根底になければならない」。
言い換えると、野心とは自身の利益を優先した執着心です。
良心とは他者への貢献を優先した使命感です。
つまり、「野心から良心へ昇華させていかなければ、せっかく起業し事業展開をしても長くは続かない」と考えているのです。
この良心とは「この世の中を変えたい」「多くの人を助けたい」といったものであり、
“公的野心”
と呼んでもよいでしょう。



私は「信念を持った使命感」と捉えています。
それでは、「起業の勘どころ」について、重要ポイントを私の体験を元にまとめてみます。
《まとめ》
~起業を成功させるための8つの勘どころ~
その1:野心を大事にせよ!
その2:独立独歩を旨とすること
その3:起業家から経営者になれ!
その4:ビジネスセンスとマネジメント力を磨け!
その5:テストマーケティングを試みる
その6:ストックとフローをバランスよく展開する
その7:ミドルリスク・ハイリターン、そしてリバレッジを意識せよ
その8:始めるときに終わり方を決めておくこと
《解説》
その1:野心を大事にせよ!
その野心は尋常でないエネルギーをもたらすことがある。



社会悪でない限り自身の野心は‟挑戦力”、‟突破力”をもたらすので大事にすることだ。
起業時の起業家の情熱は野心のもつ‟起動電力”と同じと言えよう。
起業時は無から有を生み出すために相当な‟腕力”(ばか力)が必要。
その腕力は倫理や論理では十分に発揮できない。



使命や正義でも弱い。
野心だからこそ事業は一気に立ち上がるのだ。
その2:独立独歩を旨とすること
「仲間と共同で始める」、「支援者がいて始める」、「仕事を受託できるので始める」「既に顧客をもって始める」、といったケースだ。



とても心強い態勢と言えよう。
だが、それぞれに落とし穴があるように思う。
一見、安全圏にあって事業は直ぐに軌道に乗りそうに思えるが、その心強い関係性、意外と簡単に崩れることもあり、結果、身動きができなくなって致命傷を負うことに。
「仲間と共同で始める」といったケースでは、業績が良いときは儲け配分で揉め、悪いときは借入配分で揉め、不祥事などが発生すれば途端に責任のなすり合いまで起きる。
当初は心強く思える共同態勢が、何か事が起きた時、ガラスのごとく壊れやすかったりするのだ。



もちろん例外もあるが…。
「支援者がいて始める」とは、お金を出してくれる出資者(株主)かスポンサーがいること。


この金額が大きくなればなるほど子飼いとなる可能性や、経営支配下に身を置くことになってしまう恐れもあるだろう。
「仕事を受託できるので始める」とは、起業時にすでに安定した収入源となる仕事を受託できているようなケースを指し、その保証を得ているということだ。
「下請けなのか元請けなのか?」によっては大きな違い(影響力)はあるが、一番警戒すべきは保証されていると思っていた起業時の仕事がある日突然途絶えたとき。
「既に顧客をもって始める」場合も同様。



その顧客が起業後、必ず継続されるかというとその保証はない。
元来、顧客とは浮気性と思ってよい。
の浮気性は顧客の正しい権利なのでもある。
より良いものが、より安く、より便利に手に入れば、直ぐに購入先を変えることは当然至極。



このことは極めて理に適っていると言えよう。
このように起業時に一定の恵まれた環境、条件の元、スタートすることは私の経験からも結構なリスクとなると思っている。もっとはっきり言えば弱い体質を温存することになり苦難を乗り越える力が養えないようにも思う。
世の中はそんなに甘くないのだ。
原則はやはり「裸一貫、独りで始める」、「どこまでいっても独立独歩」だ。
すべて手作りで自らの力でコツコツと積み上げることが賢明、そして尊いと思う。



その積み上げた実績こそが強靭な経営者、最強の企業へと導くのだ。
その3:起業家から経営者になれ!
野心の持つ思惑や駆り立てられている感情を経営者としての価値観に昇華させるという意味である。



感情から信念に変えると言ってもよい。
その価値観とはビジネス展開上の商道徳と企業の存在に対する社会性、そして、社員への尊厳などが要素となって構成される。
起業家魂を持ちつつも経営者としての人格を高めることは人望を厚くしていくことになる。
人望が厚くなれば会社の発展、社員の幸せにつながる。



これぞ経営者の真価と言えよう。
その4:ビジネスセンスとマネジメント力を磨け!
感性と知性と言ってよいかもしれない。
ビジネスセンスのエッセンス(本質)は、事業の新規性や差別化、そして、ビジネスモデルの独自性を主に指す。



一般的にマーケティング活動の範疇に入るだろう。
マネジメント力のエッセンスは、基本、経営資源と言われる「人・モノ・カネ・情報」の効率的な調達と効果的な運用である。
「企業は人なり」という考えが根幹だが、マネジメント力のエッセンスとなるとゴーイングコンサーンを前提とし、PL(損益計算書)以上にBS(貸借対照表)を重視した経営ができるかどうかである。
つまり、損益勘定より資産負債勘定なのだ。



そして、自己資本率の重視を意味する。
企業の存亡はこの部分で明暗が分かれる。
その5:テストマーケティングを試みる
へたにマーケティングリサーチを行った結果、成功しそうな根拠が数多く集まったとしても安心はできない。



確証はもっての外だ。
むしろ、そのような根拠は無意識の内に成功の裏づけとして集められている可能性すらある。
となればリスク“Risk”(予測可能)はデンジャー“Danger”(予測不可能)となってしまうだろう。
よって、いけると思った事業は必ず仮説検証としてテストマーケティングを行うことだ。





実際の市場に一度、期間限定で展開してみることもよい。
そこで市場に叩かれ、お客様にも叩かれ、早い段階で洗礼を受けることが成功の確率を高めると言える。
そのあと正式に再デビューするぐらいの感覚があった方が事業は成功するだろう。
その6:ストックとフローをバランスよく展開する
そのバランスは6:4ぐらいが適度な案配と思う。
勿論、業種にもよるが…。
ストック型(サブスクなどのビジネス)は一旦始めたらすぐには止められないが、うまくいけば積み上がっていくものであり利益は指数関数的に拡大する。



ビジネスのダイナミズムを味わえる。
一方、フロー型(一回ごとの単発取引)は尊いビジネスの原点。
市場と顧客のニーズに対する適応力が養える。
つまり、顧客の志向、ニーズが変化すれば提供する商品やサービスを臨機応変に変えることができるようになるということである。



正に適者生存を歩む。
その7:ミドルリスク・ハイリターン、そしてリバレッジを意識せよ
リスクを取らない限りリターンはゲットできないが、ローリスク・ローリターンでは面白くない。



旨味もない。
しかし、ハイリスク・ハイリターンでは危険すぎる。
ギャンブルに近くなってしまう。
よって、ミドルリスク・ハイリターンがチャレンジ尺度として丁度よいだろう。
そして、ビジネスの真髄は何といってもリバレッジである。



いかに最小の投資で最大の利益を得るかが醍醐味。
ミドルリスク・ハイリターンはこのリバレッジが実現でき費用対効果、投資利回りの観点らも正しい視点と言えよう。
その8:始めるときに終わり方を決めておくこと
うまくいかない状態が発生してした時、どこの時点で止めるかが決まっていれば、計画通り、客観的かつ合理的に中止や撤退ができる。



それは‟成功”とは言えなくとも“失敗”ではない。
なぜなら損害を最小限にでき、余力を持って再度、事業に再挑戦できる可能性を残すからである。
経営者の能力で一番、必要なものは決断力だ。
独断(独り決済できる)で即断できるかが企業の繁栄、衰退を決定づけると考えている。